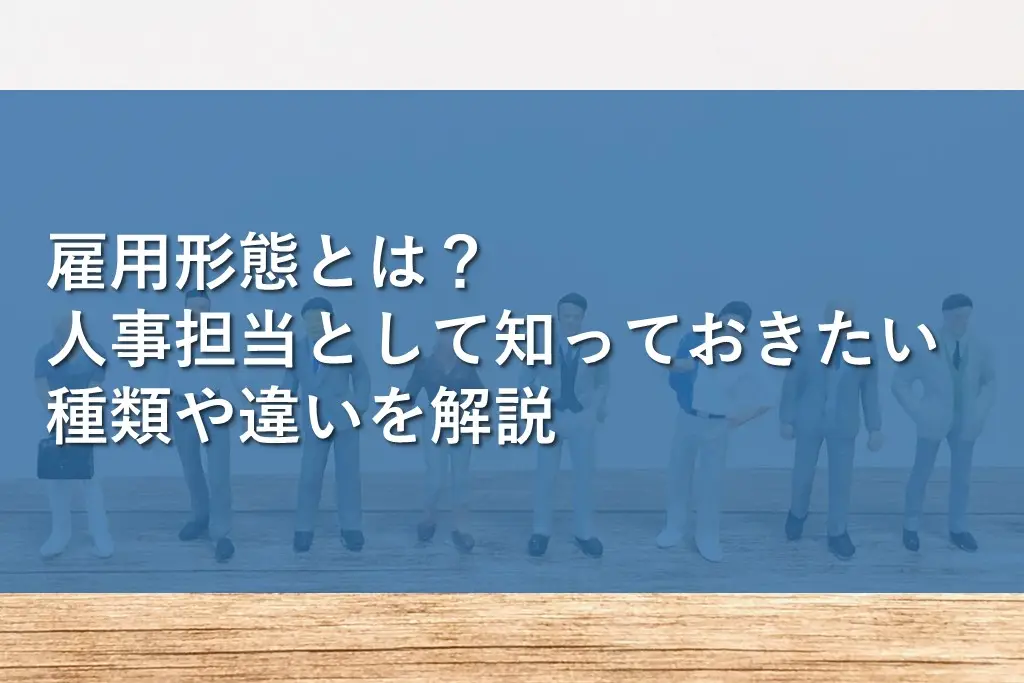
正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員といった種類がある雇用形態。
雇用形態の違いによって就業条件などが異なり、企業側にとってのメリット・デメリットも異なります。
今回は、雇用形態とは何を意味するのか、定義や雇用形態ごとの特徴に関して解説します。
また、雇用形態ごとに採用する企業側が注意すべきポイントも見ていきましょう。
雇用形態について確認する際、参考にしてください。
目次
雇用形態とは?

雇用形態とは、企業と従業員で締結される雇用契約の種類です。
雇用契約は大きく分けて、正規雇用と非正規雇用、直接雇用と間接雇用に分類されます。
さらに雇用契約の種類は、正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員に区分されていることが一般的です。
雇用形態の違いによって、労働契約で定められる期間や勤務時間などが異なります。
雇用形態に関して理解するにあたり、まずは正規雇用と非正規雇用の違い、直接雇用と間接雇用の違いを確認していきましょう。
正規雇用と非正規雇用の違い
正規雇用は無期雇用でフルタイムの契約を指し、それ以外の労働形態が非正規雇用です。
正規雇用は契約期間が定められておらず、勤務時間はフルタイムが一般的です。
ただし、正規雇用でも企業によっては短時間勤務を認めていることもあります。
非正規雇用は正規雇用以外の雇用形態で、種類はさまざまです。
契約の内容によって、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員といった雇用形態に分類され、正規雇用とは違い雇用契約の期間が決まっています。
直接雇用と間接雇用の違い
直接雇用は勤務している企業と労働者が直接契約を結んでいるケースで、間接雇用は勤務先企業と労働者の間に仲介企業が介在する契約形態です。
直接雇用は、勤務先と労働者が直接契約をしており、勤務先が労働者に対して直接給与を支払います。
正社員、契約社員、パート・アルバイトの雇用形態が直接雇用です。
これに対して、勤務先企業と労働者の間に派遣会社や請負会社が介入するのが、間接雇用です。
間接雇用は、労働派遣や業務請負が一般的で、実際に勤務する企業と給与を支払う企業が異なり、給与は派遣会社から支払われます。
雇用形態の一覧と採用時のメリット・デメリット

雇用形態は契約の種類によって、正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者に分類されます。
以下が、雇用形態が異なることによる契約内容などの違いです。
| 雇用形態 | 雇用期間 | 雇用契約 | 社会保険の加入 | 関連する法律 |
| 正社員 | 無期雇用 | 直接雇用 | 勤務先企業 | 労働基準法 |
| 契約社員 | 有期雇用または無期雇用 | 直接雇用 | 勤務先企業 | パートタイム労働法/労働基準法 |
| パート・アルバイト | 有期雇用 | 直接雇用 | 勤務先企業 | パートタイム労働法/労働基準法 |
| 派遣労働者 | 有期雇用または無期雇用 | 間接雇用 | 派遣元企業 | 労働者派遣法/労働基準法 |
ここからは、雇用形態ごとに特徴とメリット・デメリットを確認しましょう。
正社員
雇用期間の定めがなく、正規雇用として雇用主と労働契約を結んでいる労働者です。
正社員は、雇用保険や社会保険への加入が義務化されています。
また、昇進や昇給の可能性があり、退職金も支給されるなどの特徴があります。
労働時間は、所定労働時間の上限まで、フルタイムで勤務することが一般的です。
ただし、企業によっては1日6時間などの短時間勤務や、週4日勤務などを取り入れているケースもあります。
メリット
長期的に活躍してくれる人材を集めやすく、将来的な業績につなげられることがメリットです。
非正規雇用に比べて、福利厚生が手厚く安定して勤務できるため、従業員にもメリットがあります。
そのため、採用段階で優秀な人材を集めやすいことが特徴です。
また、キャリア形成などの教育も行いやすくなります。
それによって、長期的に企業へ貢献してくれる人材を育てられることも利点です。
デメリット
解雇しにくいこと、採用や教育にコストがかかることがデメリットです。
正社員は簡単に解雇することができません。
本人の能力や成果が不足していたとしても、すぐに解雇はできないため、企業としてリスクにつながることもあります。
また、正社員の雇用にはコストがかかります。
正社員は長期的なキャリア形成を行い、昇進や昇給の機会もあるため、雇用期間が長くなるほど人件費も高くなる傾向です。
契約社員
契約期間があらかじめ定められている雇用形態です。
契約期間の上限は基本的に1回あたり3年で、専門職などは5年となっています。
ただし、同じ企業での勤務期間が通算5年を超えると、本人の希望があれば無期雇用に変更しなければなりません。
勤務時間は正社員と同じ場合もあれば、契約内容によっては短時間のケースもあり、さまざまです。
福利厚生に関しては、社会保険は正社員と同様に加入しますが、住宅手当などはつかない場合もあります。
加えて、昇給がない、賞与が少ないなどのケースがあることを認識しておきましょう。
メリット
正社員よりも人件費を抑えられ、専門知識を有している人材を人員調整のしやすいかたちで採用できることが特徴です。
正社員に比べて、福利厚生にかかる費用が少なく、研修や教育にかかる費用も抑えられるため、コストがかかりません。
また、有期雇用で期間が定められているため、短期間だけ雇用するなど臨機応変な採用ができることも利点です。
デメリット
契約更新の拒否や、無期労働契約に変更したいと申し出があった際、人員調整が必要です。
契約更新をしないと従業員から申し出があった場合は、新たに採用活動をしなければなりません。
また、5年以上継続して勤務をしている契約社員を無期雇用に変更する場合にも、人員配置計画に問題がないか確認が必須となります。
人員状況を確認し、場合によっては調整が必要です。
パート・アルバイト
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用されている正社員と比較して短い労働者です。
「パートタイマー」などの呼び方もありますが、パートとアルバイトに法律上の違いはありません。
企業や個人が使い分けているだけであり、所定労働時間が短いという条件を満たせば、パートタイム労働法上の条件にあてはまります。
メリット
繁忙期など必要に応じた人員調整がしやすく、人件費の抑制につながります。
パート・アルバイトは繁忙期や閑散期などに合わせて、必要なタイミングだけ働いてもらえることが利点です。
忙しいときにだけ補助的な業務を任せることによって、正社員の残業抑制になり、人件費削減にもつながります。
デメリット
休みを調整する必要があり、入れ替わりが激しいため求人や教育の頻度が高くなります。
パート・アルバイトは、正社員と比較して想定外の休みが発生してしまう可能性もあり、そのたびに他のスタッフへお願いするなど、シフト調整をしなければなりません。
また、長期的な勤務を想定していないパターンが多く、入れ替わりに合わせて求人と教育が必要となり、手間がかかります。
派遣労働者
労働者と派遣会社が労働契約を結び、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる企業に派遣され、派遣先の指揮命令を受けて働きます。
労働者への指揮命令は派遣先の役割となりますが、賃金を支払うのは雇用契約を結んでいる派遣元です。
勤務先と雇用主が異なる複雑な雇用形態であるため、労働者派遣法によって細かいルールが定められています。
メリット
即戦力となる人材を、コストをかけずに受け入れられます。
繁忙期や業務拡大によって急に人員が必要になったとき、専門性の高いスタッフをすぐに雇い入れることが可能です。
人材の採用は派遣元が行うため、最短で即戦力となる人材を採用できます。
また、福利厚生や給与計算などの労務関係は派遣元が行うため、コストを削減できることもメリットです。
採用コストや労務管理にかかるコストを削減することで、人件費の適正化と効率化につながります。
デメリット
派遣期間が終了し人員が入れ替わるたびに、育成が必要になります。
派遣労働者には派遣期間の上限が決められており、派遣期間が終了するタイミングで新たに人員を入れ替えなければなりません。
そのため、入れ替わりのタイミングで教育が必要となり、育成コストがかかります。
また、直接雇用に比べて帰属意識が薄いことも心配されるポイントです。
モチベーションの低下や、情報ろうえいのリスクにつながるケースもあります。
雇用形態の違いで採用側が確認すべきポイント

雇用形態が違うことで、雇用する側が管理することや意識しておくべきことも変わってきます。
採用側が確認すべきポイントを、社会保険、賃金待遇、採用目的に分けてチェックしましょう。
社会保険
社会保険加入の有無は、雇用形態の違い、勤務時間や収入によって決まります。
保険の種類ごとに適用範囲をチェックしましょう。
- 健康保険・厚生年金
正規雇用だけでなく非正規雇用であっても、週の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数が一般社員と比べて4分の3以上である場合は、加入が必要です。
それ以外にも、週の所定労働時間が20時間以上、勤務期間の見込みが1年以上、月額賃金が88,000円以上、従業員が常時501人以上の企業、学生でないという5つの条件を満たす場合は加入対象です。 - 雇用保険
正規雇用・非正規雇用ともに、31日以上の雇用見込みがあり週20時間以上勤務する労働者に適用されます。
労働者が失業した際、生活の安定や再就職の支援を目的とした保険です。 - 労災保険
雇用形態を問わず、全従業員が適用範囲です。
勤務中や通勤中にケガや病気に見舞われた際に保障される制度です。
賃金待遇
法改正によって、雇用形態の違いによる待遇格差が取り締まられています。
働き方改革関連法の施行によって、パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正が決定し、2020年4月から企業規模に応じて順次導入がされています。
労働量や時間が同じであれば賃金も同じにすべきという、同一労働同一賃金の考え方が加速しており、企業側もそれに配慮した対応をしなければなりません。
採用目的
採用する目的によって雇用形態を分け、採用時は雇用形態ごとにアピールポイントを変えることが大切です。
例えば、正社員は長期的に勤務して企業に貢献してくれる人を採用します。
そのため、会社の理念、詳細な仕事内容、入社後の研修制度やキャリアプランを伝えることが必要です。
また、パート・アルバイトは、短期や短時間での雇用となり、シフトの自由さや職場の雰囲気を伝えると有効です。
採用目的や労働者の特徴に合わせて説明を工夫しましょう。
雇用形態の違いについて正しく理解しよう
雇用形態とは雇用契約の種類で、契約内容によって正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員に分類されます。
雇用形態の違いによって、雇用する側のメリット・デメリット、注意すべきポイントが異なることを認識しておきましょう。
例えば、正社員は無期雇用であるため長期的に活躍してくれる人材ではありますが、社会保険などの福利厚生や教育にコストがかかる難点もあります。
雇用形態の違いを理解したうえで、労務管理や採用活動を行うことが大切です。






 とは?
とは?