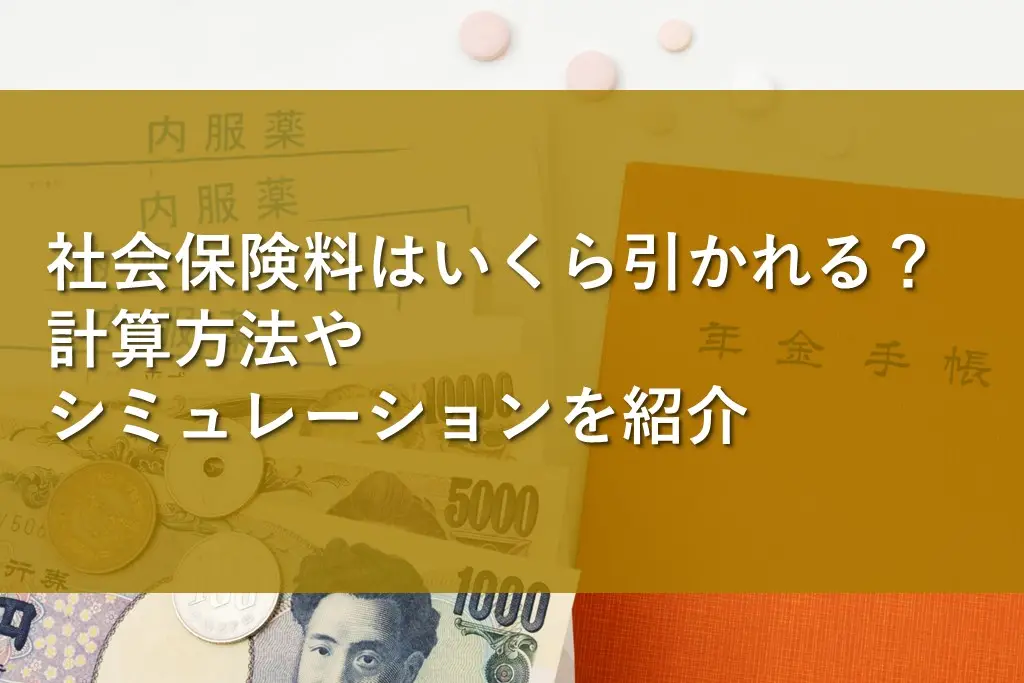
会社員の皆さんは、毎月の給与から社会保険料が天引きされていることをご存じでしょうか。
社会保険は、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、介護保険など、複数の保険で構成されています。
それぞれの保険料は、給与や賞与に保険料率を乗じて計算され、企業と従業員で按分して負担します。
では、社会保険料は具体的にいくら引かれるのでしょうか。
ここでは、社会保険料の計算方法やシミュレーションを紹介します。
目次
社会保険料はいくら引かれるのか

給与明細を見ると必ず目にする社会保険料の控除ですが、健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった各種保険料は、私たちの生活を支える重要な社会保障制度の財源となっています。
これらの保険料は給与から自動的に控除されますが、具体的にどのような制度で、どのように算出されているのでしょうか。
従業員と会社でどのように負担を分け合っているのかも併せて、詳しく見ていきましょう。
健康保険
健康保険は、会社勤めの人やその家族が加入する公的医療保険制度です。
保険料は、毎月の給与や賞与に保険料率を乗じて算出された金額を、雇用主と従業員で折半して負担します。
健康保険には加入義務があり、病気やケガをした際の医療費の自己負担が軽減されます。
厚生年金保険
厚生年金保険は、会社勤めの人が加入する公的年金保険制度です。
健康保険と同様に、毎月の給与や賞与に保険料率を乗じ、算出された金額を雇用主と従業員で折半して負担します。
年金には加入義務があり、老後の生活資金として一定額を受け取れるようになります。
雇用保険
雇用保険は、企業の従業員が失業や休業した場合に、給付金支給や就職支援を行うための保険です。
保険料率や会社の負担額は事業の種類によって異なりますが、完全な折半ではなく、従業員より会社の負担額がやや多くなっています。
従業員を雇用する企業は原則的に雇用保険に加入する義務があり、従業員は失業した際に給付や再就職の支援を受けられます。
介護保険
介護保険は、40~64歳までの従業員に加入義務がある保険です。
保険料率は健康保険組合によって異なり、従業員と会社で折半します。
将来的に介護が必要になった際に、介護保険サービスを利用する際の自己負担を抑えられます。
労災保険
労災保険は、会社の従業員が勤務中や通勤中にケガや病気、障害を負った場合の補償を提供する保険です。
他の社会保険と異なり、保険料の全額を企業側が負担します。
原則的に加入する義務があり、労働災害の発生時に申請すれば、治療費や休業補償などを受けることができます。
社会保険料で引かれる額の計算方法
社会保険料で引かれる額は、それぞれの保険によって計算方法が異なります。
| 社会保険の種類 | 計算方法 |
| 健康保険料 | 標準報酬月額×健康保険料率÷2 |
| 厚生年金保険料 | 標準報酬月額×18.3%÷2 |
| 雇用保険 | 給与や賞与の額×労働者負担分の雇用保険料率 |
| 介護保険 | 標準報酬月額×介護保険料率÷2 |
標準報酬月額とは、毎年4〜6月の賃金をベースに、従業員の給与などの平均額を等級に区分したものです。
また保険料率は都道府県ごとに、健康保険組合の場合は組合ごとに異なるため、自身の情報を個別に確認する必要があります。
社会保険料で引かれる額のシミュレーション
それでは、実際にどのくらいの金額が社会保険料として引かれるのか、シミュレーションしてみましょう。
東京都在住で年齢30歳月収30万円のケースと、同じく都内在住で年齢50歳月収50万円のケースを以下に示します。
| 東京都在住で年齢30歳月収30万円 | 東京都在住年齢50歳月収50万円 | |
| 健康保険料 | 約15,000円 | 約25,000円 |
| 厚生年金保険料 | 27,450円 | 45,750円 |
| 雇用保険 | 1,800円 | 3,000円 |
| 介護保険 | 0円 | 約4,000円 |
このとおり、年齢や収入によって、社会保険料の負担額は大きく変わってくるのです。
社会保険料は月いくら引かれるかを知って参考にしよう
社会保険料は、将来の備えとして重要な役割を果たしています。
健康保険や厚生年金保険、雇用保険、介護保険などの社会保険は、保険ごとに保険料の計算方法が異なります。
健康保険料は標準報酬月額×健康保険料率÷2、厚生年金保険料は標準報酬月額×18.3%÷2、
雇用保険は給与や賞与の額×労働者負担分の雇用保険料率、介護保険は標準報酬月額×介護保険料率÷2です。
会社の所在地の都道府県や加入している健康保険組合によって保険料率が異なるので注意しましょう。
自分の年齢や収入に応じて、どのくらいの社会保険料が引かれるのかを把握しておくことをおすすめします。







 とは?
とは?