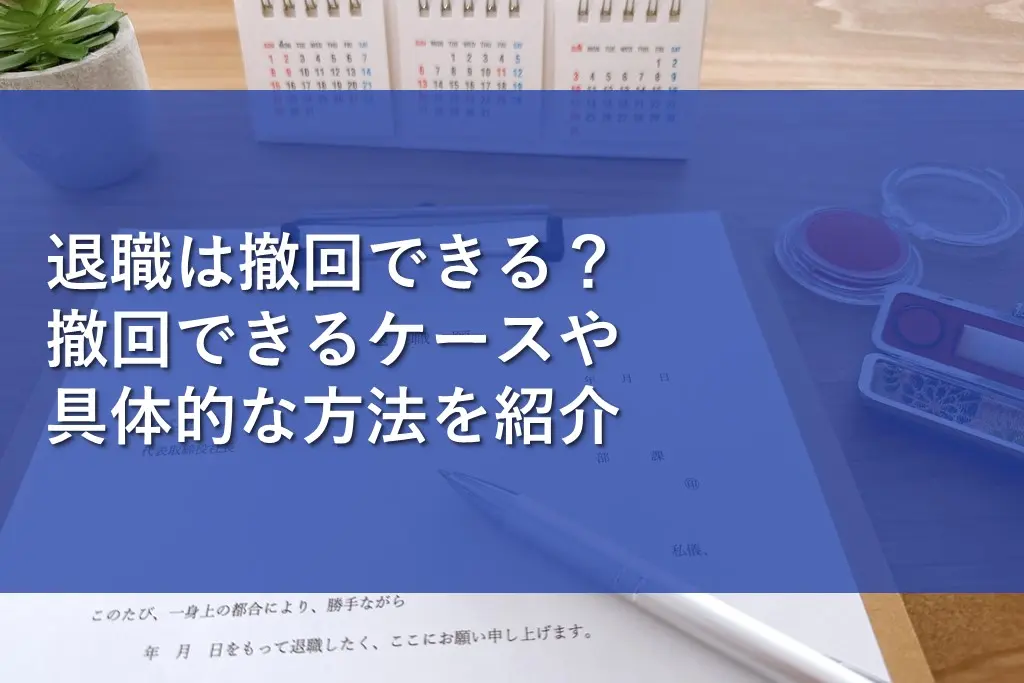
退職の申し出をしたあとに、何らかの事情があったとして退職撤回はできるのでしょうか。
実は、条件やタイミングによっては退職を撤回できる可能性があります。
強迫など理由次第では法律の定めるところにより退職取消が可能になるため、条件にあてはまる方は証拠を集めておきましょう。
この記事では、退職ができるケースとできないケース、具体的な撤回方法を詳しく解説しています。
目次
退職を撤回できるケース

退職の申し出を撤回するには、以下の条件とタイミングを満たしていることが必要です。
- 合意退職の場合:会社が承認する前まで
- 自主退職の場合:会社が受理する前まで
それぞれのケースについて、注意点と併せて詳しく解説します。
合意退職の場合は会社が承認する前まで
合意退職の場合、会社が承認する前であれば退職の撤回ができます。
合意退職とは、労働者の退職申入れに対して会社が承認して、労働契約を解消することです。
退職が承認されてしまった場合、労働者一人の意思だけで退職を撤回することはできません。
いつ退職の意思が承認されるかは労働者にはわからないので、撤回を希望する場合は速やかな対応が必要になります。
また、小規模企業であるほど承認の意思が社長まですぐに伝わりやすいため、注意しましょう。
自主退職の場合は会社が受理する前まで
自主退職の場合、会社に退職の旨が受理される前であれば撤回できます。
自主退職とは、労働者から一方的に労働契約を解消することです。
企業側の承認は必要ないため、退職届が受理された時点で退職の効力が発生します。
一方的な労働契約の解消について、「意思が変わったので働きたい」「やはり辞めたい」など、意思が頻繁に変わると企業が不利益を被りかねません。
このことから、民法第540条にて上記のようなルールが定められています。
期間に定めのない社員なら、退職の申入れから2週間経過後に退職となるのが一般的です。
退職が撤回できないケース
上述でも少し触れたとおり、いつでも退職を撤回できるわけではありません。
合意退職と自主退職それぞれについて、退職が撤回できない場合を紹介します。
いずれの退職方法でも、承認・受理されたあとでは基本的に撤回は不可能と覚えておきましょう。
合意退職で会社が承認したあと
合意退職の場合、会社が承認したあとは撤回ができません。
合意退職は双方の合意のもと退職しているはずなので、一方の当事者が合意なしに撤回することは不可能です。
人事の決裁権(社長や人事部長)が退職の意思を承諾し、それを労働者本人に伝えたあとであれば、会社側が撤回に応じることは基本的にないでしょう。
ただし、社長ではなく部門長などが承諾を行った場合は、無効にできるかもしれません。
また、退職届より退職願のほうが撤回の余地があるともいわれています。
自主退職で会社が受理したあと
自主退職の場合、退職の意思を会社が受理したあとでの撤回は不可能です。
自主退職は労働者からの一方的な労働契約の解消となるので、会社の承認は発生しません。
つまり、会社が受理した時点で退職になります。
このとき、会社のなかの誰が受け取った時点で受理となるかが重要です。
社長本人の受理であれば確実ですが、それ以外の役員などが受け取った時点で受理となるかは、企業ごとに異なります。
退職の取消が法律によって認められるケース
タイミングによらず退職の取消が認められるケースは、下記のとおりです。
- 錯誤(勘違い):労働者本人の意思と一致しないまま退職の意思表示をした
- 詐欺:虚偽の事実を信じさせて労働者に退職を迫った
- 強迫:労働者に恐怖心を与える言動をして退職に追い込む
上記の場合は民法95条、96条の定めるところにより、退職の取消が認められる場合があります。
しかし、取消のためには労働者側でこれらの証明をしなければなりません。
錯誤や詐欺、強迫などの事実を確認できる証拠を集める必要があります。
パワハラなど該当の行為があった際は、あらかじめ録音をしておくのがおすすめです。
錯誤(勘違い)による退職の取消
錯誤による退職の取消が認められるケースとして、退職の意思が誤った判断に基づいて行われた場合などがあります。
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
引用:民法(e-Gov法令検索)95条1項
端的にいうと、解雇になるような事実はないにも関わらず、労働者本人が退職しなければならないと勘違いして退職の意思を表示してしまったということです。
例えば「このままだと懲戒免職になって退職金も払えないが、退職届を出してくれれば退職金を渡せる」と説得されて退職届を提出した場合などは、錯誤に該当します。
詐欺による退職の取消
騙されて認識とは違う意思表示をしてしまうようなケースでは、退職の意思表示を取り消すことが可能です。
民法96条1項にて、詐欺による退職の意思は撤回できる旨が記載されています。
具体例としては「近々会社が倒産するので来月の給料を支払えない」と言われたため退職を申し出たものの、経営不振の事実はなかったという場合は詐欺に該当するでしょう。
強迫による退職の取消
強迫による退職とは、脅しによって恐怖した結果、誤った意思表示をしてしまうことです。
詐欺による退職の取消と同様、民法96条1項にて強迫による退職の意思表示も撤回ができるとされています。
大声を出したり物を蹴ったりして退職を迫られた、長時間一室内に拘束されて退職を推奨された場合などは強迫に該当するでしょう。
たとえ刑法第222条第1項の脅迫罪にあたらなかったとしても、民法を理由に退職を取り消せることがあります。
退職を撤回するための具体的な方法
退職を撤回する方法としては、下記の二つが一般的です。
- 退職撤回通知書を提出する
- 口頭で退職を撤回する
ただし、口頭での撤回ではトラブルに発展するケースもあります。
不要なトラブルを回避するためにも、できれば退職撤回通知書を用意しましょう。
退職撤回通知書を提出する
退職の撤回を考えた際、退職撤回通知書を提出するという方法があります。
口頭での退職の撤回に比べると、「言った」「言わない」のようなトラブルを減らせる点がメリットです。
基本的には退職撤回通知書を提出し、文章で伝えたほうが確実でしょう。
退職撤回通知書のテンプレートは以下のとおりです。
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇区〇町
〇番〇号〇〇ビル〇階
〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長 〇〇〇〇殿
退職願の撤回通知書
私は、貴社に対し、令和〇年〇月〇日付け退職願をもって退職を希望する旨を申し込みました。しかしながら、その後、再度十分に思慮した結果、今後とも貴社で勤務を継続したいと決断するにいたりました。
よって、令和〇年〇月〇日付けの私の作成にかかります前述の退職願は、これを撤回させていただきます。
上記のとおり、ご通知いたします。
以上
令和〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇区〇-〇
〇〇〇〇株式会社 〇〇部〇〇課
〇〇〇〇 印
撤回をした時点で退職願や退職届の効力はなくなります。
退職を前提として引き継ぎを行ったり、書類にサインしたりといった行動を安易に行わないよう注意しましょう。
口頭で退職を撤回する
人事決定権のある上司に口頭で退職の撤回の意思を伝えることで、退職の撤回ができるかもしれません。
口頭の場合は、退職の撤回をする意思がわかるよう内容を詳しく伝えることが重要です。
注意点として、口頭でのやり取りは水かけ論に発展する可能性があり、退職を撤回できたとしてもわだかまりが残るかもしれません。
そうしたトラブルを回避するためにも、口頭で意思を伝えるだけでなく、退職撤回通知書も提出しておくのがベターです。
退職を撤回したその後の気まずい状況の解消法
退職を撤回できたとしても、噂が広まってしまっていると、その後は社内で気まずい状況に追い込まれることがあります。
このとき、社内でどのように立ち振る舞うのが良いのでしょうか。
退職撤回後に気まずい状況を打破する方法を、下記でご紹介します。
なお、円満退職をめざす場合であれば、適切なタイミングに退職を伝えることが大切です。
次の記事で退職を伝える際のポイントや注意点、具体的な伝え方を解説しているので、参考にしてみてください。
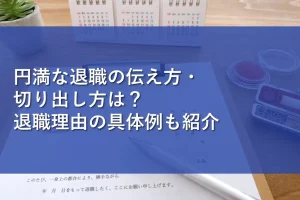
圧倒的な成果を挙げる
圧倒的な成果を挙げることで会社に必要な人材だと思わせて、気まずい状況を解消できることがあります。
退職しようとした事実は同僚や上司には伝わっているかもしれませんが、あの人がいてくれて良かったと思ってもらうことができれば、自分を取り巻く空気も変わるかもしれません。
割り切って気にしないようにする
自分は自分だと割り切って気にしないことで、気まずい状況を解消できる人もいます。
成果を挙げて認められるのが手っ取り早いとはいえ、誰もがそう簡単にいくわけではありません。
この場合は同僚や上司にどう思われても気にしないという、ある種開き直った姿勢をとるのも一案です。
こつこつと地道にがんばっていれば、理解してくれる人は現れます。
自分のためにも、気まずいからといって転職の目途が立たないまま退職するようなことは避けましょう。
退職を撤回したい際は、タイミングと方法に注意しよう
退職の撤回をする場合には、タイミングが重要です。
撤回の具体的な方法には文書・口頭の二つがありますが、口頭の場合でも退職撤回通知書を用意することをおすすめします。
この場合、人事決定権のある上司にできる限り早く撤回の意思を伝えましょう。
ただし錯誤、詐欺、強迫といった民法に違反する行為の証拠を持っている場合、タイミングによらず退職の撤回が認められるかもしれません。
このケースでは弁護士や労働組合、労働局へ相談してみてください。






 とは?
とは?