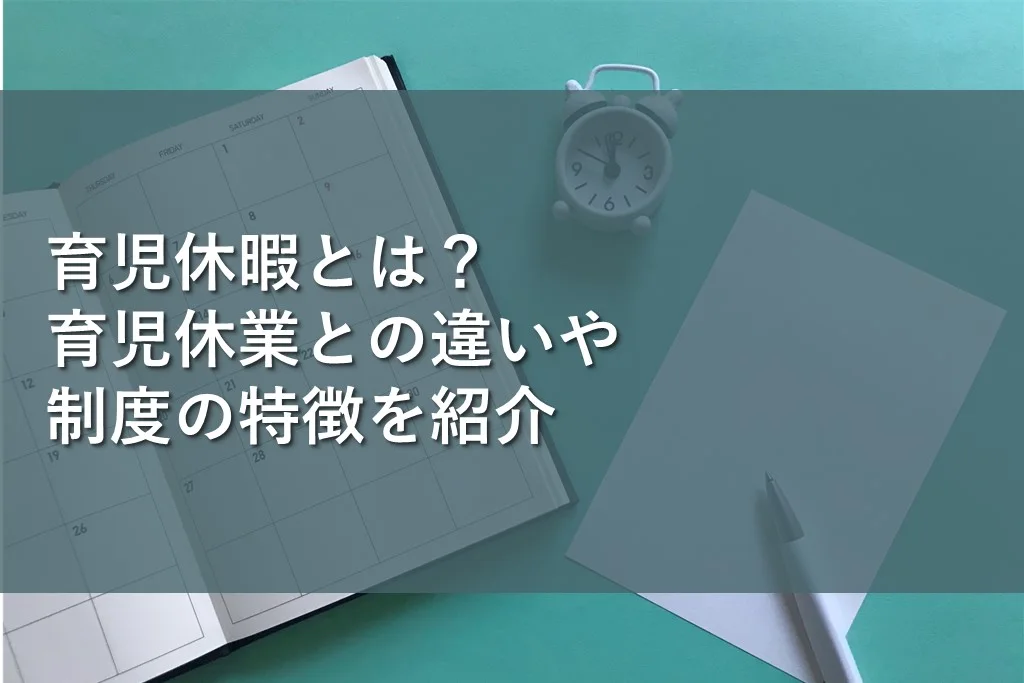
育児休暇は、従業員が子育てをしやすくするための制度であり、近年多くの企業で導入が進められています。
育児休業とは異なり、育児休暇は法律で定められた制度ではないため、企業によって制度の有無や内容はさまざまです。
本記事では、育児休暇の概要や育児休業との違い、企業が導入するメリットなどについて詳しく解説します。
目次
育児休暇とは

育児休暇とは、従業員が子育てをしやすくするために企業が独自に設ける、休暇制度のことです。
2022年に改正された育児・介護休業法では、小学校就学前の子どもを持つ労働者に対し、育児目的の休暇制度を整備することを企業の努力義務としています。
ただし、あくまで努力義務であるため、制度の有無や対象者、期間などの詳細は企業ごとに異なります。
育児休暇の具体的な内容は、企業の就業規則や労使協定などで定められることが一般的です。
育児休暇と育児休業の違いは?
育児休暇と育児休業は、ともに子育て中の従業員を支援するための休暇制度ですが、いくつかの違いがあります。
以下では、それぞれの制度の特徴について詳しく見ていきましょう。
育児休暇
育児休暇は、企業が独自に定める制度であるため、対象者や期間、給付金の有無などは企業によってさまざまです。
例えば、子どもが1歳になるまでの間に数日間の有給休暇を付与する企業もあれば、小学校就学前まで利用できる休暇制度を設けている企業もあります。
制度の内容は就業規則などで確認することが必要です。
育児休業
一方、育児休業は育児・介護休業法に基づく制度です。
原則として子どもが1歳になるまでの間に、労働者は2回までの育児休業を取得できます。
保育園に入れないなどの理由がある場合は、最長で子供が2歳になるまで育児休業を延長することも可能です。
育児休業は法律で定められた制度であるため、企業の就業規則に関わらず、対象者は制度を利用できます。
さらに、育児休業を取得した労働者は、原則として育児休業給付金を受け取ることが可能です。
育児休暇を導入するメリット
育児休暇制度の導入は、企業にとってもいくつかのメリットがあります。
ここでは、従業員の定着率向上や採用力の強化といった観点から、育児休暇の意義について解説します。
従業員の定着率向上
育児休暇制度を整備することで、従業員の定着率を高められます。
出産や育児は、多くの人がライフイベントとして経験するものですが、仕事との両立に不安を抱える従業員も少なくありません。
企業が育児休暇制度を充実させることで、従業員は安心して仕事と育児を両立できるようになるでしょう。
その結果、従業員の満足度や企業へのロイヤルティが高まり、長期的な定着率の向上が期待できます。
採用力の強化
育児休暇制度は、企業の採用力強化にもつながります。
特に、これからライフイベントを控えている若年層の採用においては、育児休暇制度の有無は大きな関心事項です。
充実した育児休暇制度を整備し、働きやすい環境をアピールできれば、優秀な人材の獲得に有利になるでしょう。
加えて、育児休暇制度は女性の活躍推進にも寄与するため、企業イメージの向上にもつながります。
育児休暇の対象期間の目安
育児休暇の対象期間に法律上の定めはありませんが、一般的な制度例としては以下のようなものがあります。
- 子どもが1歳になるまでの間に、最大7日間の有給休暇を取得できる
- 子どもが3歳になるまでは育児休暇を利用でき、小学校3年生までは労働時間の短縮などの育児支援制度を利用できる
- 出産時および子どもが1歳になるまでに、3日間の特別休暇を取得できる
企業によって、育児休暇の対象期間や利用可能な休暇日数はさまざまですが、子どもの成長に合わせた柔軟な制度設計が求められます。
育児休暇を企業で導入する際の注意点
育児休暇制度を導入する際には、いくつかの注意点があります。
制度の周知徹底や、ハラスメント防止、不利益な扱いの禁止などについて解説します。
制度の周知徹底
育児休暇制度を導入した場合、従業員への制度の周知を徹底することが重要です。
制度の周知が不十分だと、せっかくの制度も有効に機能しません。
社内報やイントラネットなどを活用し、制度の内容や利用方法について従業員に広く伝えることで、制度の活用が促進されます。
ハラスメントの防止
育児休暇制度の利用者に対する、ハラスメントを防止するための対策も必要です。
育児休暇の申請を理由とした嫌がらせや、申請の取り下げを求めるような行為は厳に慎まなければなりません。
ハラスメント防止のための社内研修や相談窓口の設置など、適切な対策を講じることが求められます。
不利益な扱いの禁止
育児休業については、休暇利用を理由とした不利益な扱いを法律で禁止しています。
育児休暇でも、取得を理由に、昇進を遅らせたり、評価を下げたりするようなことがあってはなりません。
公平な評価制度を整備し、育児休暇の利用が不利益につながらないよう、十分な配慮が必要です。
育児休暇制度の導入を検討しよう
本記事では、育児休暇制度の概要や育児休業との違い、企業が導入するメリットなどについて解説してきました。
育児休暇は法律で義務付けられた制度ではありませんが、従業員の仕事と育児の両立を支援し、定着率や採用力の向上につながる有意義な取り組みです。
一方で、制度の周知徹底やハラスメント防止、公平な評価制度の整備など、導入時の注意点にも十分に配慮する必要があります。
育児休暇制度の導入を検討し、従業員が安心して働ける環境づくりを進めていきましょう。







 とは?
とは?